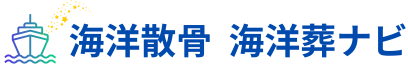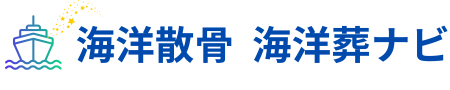海洋散骨は、環境に配慮しながら適切に行えば、海への悪影響を最小限に抑えることができます。
しかし、方法を誤ると環境問題や海洋生態系への負担を引き起こす可能性もあります。
ここでは、海洋散骨が海に与える影響について詳しく解説します。
海洋散骨の環境負荷のポイント

海洋散骨が環境に与える影響は、主に以下の3つの観点から考えられます。
- 遺骨の成分が海水や生態系に影響を与えるか
- 散骨に使用する副資材(骨壷や花、布など)が環境に負荷をかけるか
- 海洋散骨をするエリアが適切か(漁業や海水浴場への影響)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
遺骨の成分と海洋環境への影響
遺骨の主成分は環境に悪影響を与えるか?
人の遺骨の主成分はリン酸カルシウム(Ca₃(PO₄)₂)であり、これは貝殻やサンゴと同じ成分です。
- 水に溶けにくいため、すぐに海水と化学反応を起こすことはない
- 適切に粉骨すれば、海底に沈み自然に分解される
- 生態系に悪影響を与える有害物質は含まれない(通常の骨の場合)
したがって、粉末状にして適切な海域で散骨する限り、遺骨そのものが環境に悪影響を及ぼすことはほぼないとされています。
遺骨の大きさが海への影響を左右する
- 2mm以下の粉末状にすれば、海底に沈みやすく拡散しにくい
- 大きな骨片が残っていると、海岸に流れ着く可能性がある
- 完全に粉骨していないと、漁網に引っかかるなどの問題が発生することも
そのため、多くの海洋散骨業者では、粉骨(直径2mm以下のパウダー状)にしてから散骨することを推奨しています。
副資材(花や骨壷など)が海洋汚染につながる可能性
海洋散骨の際に、花や布、骨壷などの副資材を使うことがありますが、これらの扱いを間違えると海洋汚染につながる可能性があります。
骨壷の使用は原則NG
- 陶器や金属製の骨壷は海底に沈んでも分解されないため、環境汚染につながる
- 竹や紙製の「水溶性骨壷」もあるが、完全に溶けるまで時間がかかることがあり、環境負荷を考えると推奨されない
- 基本的には遺骨だけを散骨するのが最も環境に優しい方法
花を撒く場合は自然に還るものを選ぶ
- 生花はOKだが、茎やリボンはNG(茎が長いと漁船のスクリューに絡むことがある)
- 造花やラッピング素材のリボンは絶対にNG(海洋プラスチックごみ問題につながる)
- 花びらのみを撒くのが最も環境負荷が少ない
布や手紙を流すのは環境負荷の観点から避けるべき
- 「最後のお別れに手紙を海に流したい」と考える人もいるが、紙類は完全には分解されず、マイクロプラスチックの原因になる可能性があるため避けたほうがよい。
海洋散骨の場所と漁業・観光への影響
散骨する場所のルールと漁業への影響
日本では、海洋散骨を行う際に法律で明確な禁止事項はないが、一般的なマナーとして以下の点が求められる。
- 漁業や養殖が行われている海域は避ける(衛生的な観点から問題視されることがある)
- 海水浴場の近くでの散骨は避ける(風評被害を防ぐため)
- 陸地から十分に離れた沖合で行う(通常2~3海里=約3.7~5.5km沖合)
これを守らないと、地元の漁業関係者や観光業界とトラブルになることがあるため、事前にルールを確認し、許可を得ることが大切。
海流の影響を考慮する
- 適切な場所で散骨しても、海流によって遺骨が流れつく可能性がある
- 風向きや潮の流れを考えずに散骨すると、予想外の場所に影響を与えることもある
- 専門の海洋散骨業者は、潮流や風向きを計算して適切な海域を選定するため、できるだけ専門業者に依頼するのが望ましい
海洋散骨が海に与える影響を最小限にする方法
- 2mm以下の粉末状にする(大きな骨片を残さない)
- 骨壷は使用しない(遺骨だけを撒く)
- 花を撒く場合は花びらのみを使用(造花・茎・リボンはNG)
- 海水浴場や漁場を避け、十分に沖合で散骨する
- 潮流や風向きを考慮する(経験豊富な専門業者に相談する)
まとめ
■遺骨そのものは環境に悪影響を与えないが、粉骨して適切に撒く必要がある。
■骨壷や花、手紙などの副資材は海洋汚染の原因になるため、使用に注意する。
■散骨場所の選定を誤ると、漁業や観光に悪影響を与える可能性があるため、適切な沖合で行うことが重要。
■海洋散骨を行う際は、環境に配慮し、ルールを守ることが大切。
適切に行えば、海洋散骨は故人を自然に還す環境に優しい供養方法となります。ルールとマナーを守りながら、自然と共生できる形での散骨を考えていきましょう。