生活保護を受給している方や、そのご家族から「お墓を建てる余裕はないが、亡くなった後にきちんと供養をしたい」という相談が増えています。特に海洋散骨は、自然に還るシンプルな葬送方法として注目されていますが、「生活保護でも利用できるのか?」「費用はどうすればよいのか?」という疑問を持つ方は少なくありません。
この記事では、生活保護を受けながら海洋散骨を希望する場合の制度・費用・注意点について詳しく解説します。
◎この記事でわかること◎
- 生活保護と葬儀に関する制度
- 生活保護世帯が海洋散骨を選ぶメリット
- 海洋散骨の費用相場と生活保護世帯での利用方法
- 生活保護世帯が海洋散骨を利用する際の注意点
- 生前契約の流れ
- よくある質問
生活保護と葬儀に関する制度
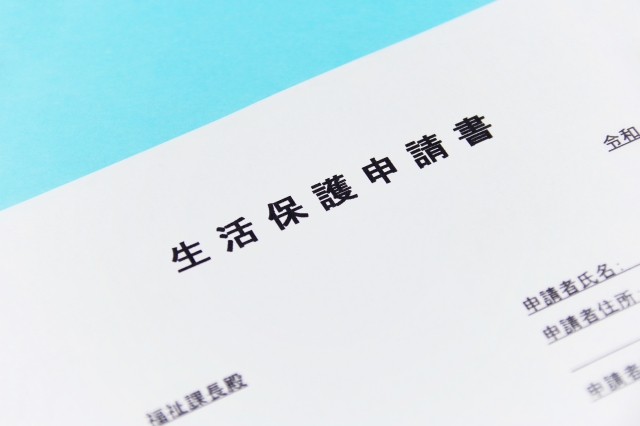
葬祭扶助とは?
生活保護法には「葬祭扶助」という制度があり、生活保護受給者が亡くなった際に最低限の葬儀費用を支給してもらえる仕組みがあります。
支給対象:生活保護を受けていた本人や、その扶養義務者が葬儀を行う場合
支給額の目安:20万円前後(自治体によって異なる)
使用目的:火葬、収骨容器、運搬費用など葬儀に最低限必要な費用
海洋散骨は葬祭扶助の対象になる?
葬祭扶助はあくまで「火葬を行い、最低限の葬儀を執り行うための費用」に限定されます。そのため、海洋散骨そのものの費用は原則として葬祭扶助の対象外です。
ただし、火葬費用や遺骨の引き渡しに必要な部分は葬祭扶助でまかなえるため、残りの「散骨費用」を自費で負担する形になります。
生活保護世帯が海洋散骨を選ぶメリット
墓地・永代使用料が不要
お墓を建てる場合、数十万円~数百万円の費用がかかりますが、海洋散骨ならその負担を避けられます。
管理費用がかからない
お墓や納骨堂では毎年の管理費が必要ですが、海洋散骨は一度行えば追加費用はかかりません。
シンプルで心に残る供養が可能
「海に還る」という自然な形での供養は、経済的な制約があっても心の区切りをつける方法として選ばれています。
生前契約の注意点
契約先の信頼性を確認する
海洋散骨はまだ新しい分野のため、業者によってサービスの質や信頼性に差があります。過去の実績や口コミ、行政からの許可状況を確認しましょう。
契約内容の詳細をチェックする
-
散骨場所が明確に指定されているか
-
代金に含まれるサービス内容(船代、粉骨代、証明書発行など)が明記されているか
-
キャンセルや契約解除の条件はどうか
永久的な保証があるか
会社が将来存続しているとは限りません。そのため、信託や提携団体を利用して「会社がなくなっても契約が有効」という仕組みを整えている業者を選ぶと安心です。
海洋散骨の費用相場と生活保護世帯での利用方法
| 委託散骨(代理で散骨してもらう) | 5万~10万円程度 |
| 合同散骨(他の方と一緒に乗船して散骨) | 10万~15万円程度 |
| 個別散骨(チャーター便で家族だけで実施) | 20万~40万円程度 |
生活保護世帯での現実的な選択肢
生活保護を受けている場合は、もっとも費用を抑えられる委託散骨や合同散骨を選ぶケースが多いです。
特に委託散骨であれば数万円で利用でき、家族に大きな負担をかけずに済みます。
生活保護世帯が海洋散骨を利用する際の注意点
自治体に事前相談する
葬祭扶助の範囲や手続きは自治体ごとに異なります。海洋散骨を希望する場合は、生活保護を担当する福祉課に相談しておきましょう。
葬儀社・散骨業者と連携する
葬祭扶助を利用する火葬と、海洋散骨の流れをスムーズにつなげるために、福祉葬を扱う葬儀社と散骨業者の両方に事情を伝えることが大切です。
費用を分けて考える
火葬や骨壺は葬祭扶助の対象
海洋散骨は自費(ただし費用は少額)
という形で区分することで、無理のない形で実現できます。
よくある質問
生活保護を受けていても、家族が費用を出せば海洋散骨はできる?
できます。葬祭扶助で火葬をまかなった上で、家族が追加費用を負担すれば散骨が可能です。
散骨の費用を分割払いできる業者はある?
一部の業者では分割払いや後払いに対応している場合があります。相談時に確認するとよいでしょう。
散骨を内緒で行うことは可能?
法的に問題はありませんが、生活保護の給付を受ける際には自治体との連携が必要になるため、事前相談をおすすめします。
まとめ
生活保護を受けていても、火葬部分は葬祭扶助でまかなえ、散骨費用は自費で負担することで海洋散骨を行うことは可能です。費用を大きくかけずに自然に還る供養ができるため、お墓を建てられない家庭にとって現実的な選択肢となります。
「できるだけ家族に迷惑をかけず、シンプルな供養をしたい」と考える方は、まずは自治体や散骨業者に相談し、最適なプランを検討してみてください。

